2025.10.03 [みそまろコラム]
【日本の伝統!鰹節の魅力に迫る〜歴史編〜】

まいどおおきに。みそまろです。ぺこり。お味噌汁作りに欠かせないものといえば、やはり「味噌」かと思いますが、2番目には「お出汁」ではないでしょうか。お味噌汁にしても、お湯に味噌を溶いただけのより、お出汁に溶いたお味噌汁のほうが、旨味、香り、満足感、いずれもお月さんとすっぽんの差で軍配が上がるかと思います。
そのお出汁の代表格といえば「昆布・干し椎茸・鰹節」かと思いますが、実はこの3つのうちひとつは「発酵食品」ってご存じでしたか?
実は、鰹節の中の「本枯節」と呼ばれるものが、発酵食品なのです。
今回からは、その「本枯節」も含めた鰹節ワールドをみなさまにお楽しみいただこうと思います!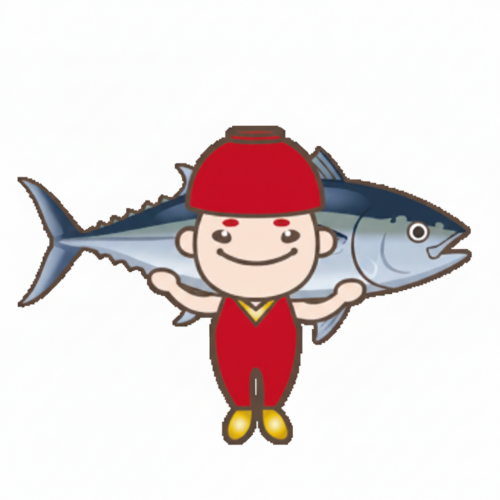
聖徳太子も食べていた?鰹節のはじまり
むかーしむかし、縄文時代から海の幸を愛していた我々日本人。当時の貝塚などからは、貝のみならず、鰹の骨も見つかっているそうです。釣ってきた鰹は保存性を高めるために塩漬けにし、乾燥させていたそうですが、その名も「堅魚(かたうお)」。「かつお」という名前の由来もここからきていそうですよね。堅魚は、飛鳥時代にも食べられていたらしいので、もしかすると聖徳太子はんも食べていたかもしれませんね。
その飛鳥時代から続く奈良時代にかけては、当時の木簡や『延喜式』などの文献によれば、鰹を煮てから天日干しをする「煮堅魚(にかたうお)」という加工方法があったと記されています。
その「煮堅魚(にかたうお)」を煙で燻すようになったのは、室町時代に入ってからと言われています。囲炉裏の上に吊るして煮炊きする熱や煙で燻して乾燥させる「焙乾(ばいかん)」あるいは「燻乾(くんかん)」と呼ばれる方法が編み出され、現在の鰹節に近いものが作られるようになったそうです。
鰹節を燻した男たち:角屋甚太郎親子の知恵
時はぐーんと進んで江戸時代、より本格的な鰹節が登場します。その立役者は、和歌山沖から高知沖を行き来しながら漁をしていた、和歌山県印南町の漁民、角屋甚太郎はん。
初夏から秋にかけて大量に獲れる鰹を保存するために、煮て乾かすだけでなく、煙で燻す「燻乾法(くんかんほう)」を開発。設備も整えて、現在の荒節に似た鰹節を作り出しました。
その後、息子の二代目・角屋甚太郎はんがさらに改良を加え、青カビをつけて日光乾燥を繰り返す「燻乾カビ付け法」を編み出したことで、今の鰹節に近い形が完成。これは「熊野節」として人気を博し、美食の都である京都や、天下の台所と言われた大阪の富裕層にも大層喜ばれたそうです。
角屋甚太郎親子が編み出したこの技術は、高知県や鹿児島県の枕崎や房総・伊豆などに広められたそうですよ。
毒をもって毒を制す!?土佐節の逆転劇
ところが、大問題が発生です。
高知県や鹿児島県で作られた鰹節は、大阪や江戸へ船で長期間かけて輸送されていたのですが、その間に潮風や湿気で悪性のカビが生えてしまうことがあったそうなんです。つまり、大切な商品が腐って売れなくなってしまうということ。これは由々しき事態!
そこで二代目はんが考えたのは「毒をもって毒を制す」方法。
悪いカビがつかないように、最初から良いカビを鰹節に付けてしまう「焙乾カビ付け法」という方法でした。この工夫によって、悪性のカビを防げるだけでなく風味もぐっと良くなって、「土佐節」という名前で一躍人気商品に!長期輸送でも味が落ちにくかったことから、土佐藩を代表する貿易品にもなったそうです。
やがてこの「土佐節」の作り方が全国に広まり、明治時代には品評会が開かれるようになって、技術もどんどん進化&磨き上げられていきました。自然にカビがつくのを待つのではなく、育てたカビの胞子を吹き付ける方法に変わったことで品質も安定するようになり、これが今の鰹節づくりの定番の方法になったそうです。
昔の人の知恵と工夫が、今の食卓につながっていると思うと、なんだか感慨深いですね。
角屋甚太郎親子の功績がなければ、今の鰹節はなかったかもしれません。
海の恵みを守るために生まれた知恵、そして問題が起こっても機転を効かせてその壁を乗り越えてくれたおかげさまで、「鰹節」が時代を越えて日本中に広がっていったわけです。
鰹節には、そんなドラマチックな歴史があったんですねえ。
さて次回は、この鰹節の作り方をご紹介し、ますます鰹節ファンになっていただきたいと企んでおりますよ。どうぞお楽しみに。
参考図書:理由がわかればもっとおいしい!発酵食品を楽しむ教科書 ナツメ社





